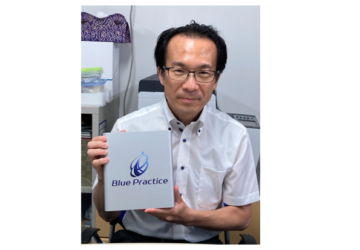農工大NEXT
独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)で働き、ハードではなくソフトのアプローチからまちづくりを実践する大矢知真貴さん(地生H24)。
地域住民のお困りごと解決を目指し、“ソフトなまちづくりの実証実験”を行なっている。
UR都市機構の新規事業公募において、子育て世帯の課題を解決するアイデアが採用され、2024年8月から、実証実験「団地キッチン」田島(さいたま市)を運営する日本総合住生活(株)の協力を得て、取り組みを開始している。豊かな暮らしの社会実装に向けた挑戦について、お話を聞いた。

現在のお仕事について
今のお仕事を教えてください
地域住民のウェルビーイングを高めるまちづくりを行っています。
ある場を誰がどう使うかを考えることから始めて、住民のお困りごとを解決したいと思っています。
現在は、「子育ての負担を減らし、地域に居場所を作って豊かな暮らしを実現すること」を目指す子育て世帯向けの実証実験を行っています。
具体的には、地域住民が子どもの食事の見守りをサポートするサービスを行なっています。
昔いた“地域のおせっかいおばさん/おじさん”を現代版にアレンジしたようなイメージです。
実施予定の施策としては、「見守りごはん」と称して、地域住民等が子育て世帯のサポーターとなり、子どもの食事介助や送 迎、見守りを行います。仕事で遅くなった時や息抜きしたい時など、子育て世帯の日々の生活をサポートします。
▶詳細な取り組み内容はこちらから
https://www.ur-net.go.jp/aboutus/press/ip8i2r0000005ofy-att/ur2024_press_0719_co.pdf
こういった取り組みが団地のプロモーションとブランディングにもつながれば、団地に住む人が増えるのではないかと考えています。

子育て”の分野に挑戦したきっかけを教えてください。
「子育ては家庭内で完結させないといけない」という呪縛を解きたかったからです。
言い換えると、子育てを頑張っている親が地域に頼れる仕組みを作りたいです。
“子育て”ってとても忙しいんです。
ただ、お母さん/お父さんが「自分達だけで何とかしなくてはいけない」と自身を追い込んでいることが多い印象です。
そんな子育て世帯の呪縛を解いて、子育てをしながらも豊かな暮らしを実現しようと考えています。
実証実験において気をつけていることはありますか?
このプロジェクトでは、日常にいかに溶け込めるかを重視しています。
子どもを預ける仕組みだと、預ける側、預けられる側にハードルがあると思います。
日常的に行う食事という、ハードルの低い場面を接点にできないかと考えました。
子育て中の食事はカオスなんです。(笑)
楽しいはずの食事も億劫になってしまいます。
そこで、食事をテーマに子育て世帯の課題解決のために考えたのが“見守りごはん”という取り組みです。
地域に根ざしたプロジェクトにするため、地域の方とのコミュニケーションをしながら地道に進めています。

ご自身もお子さんがいらっしゃる中で、お仕事で意識していることはありますか?
「自分にはできない」と思って選択肢を狭めないようにしています。
一人目の子どもの時は時短勤務にしていましたが、そうすると新しいことに挑戦しづらくなってしまいました。
「できない」ではなくて「どうすればできるか?」を考えるようになりました。
家庭内で頑張るだけでなく、外部を頼って踏ん張った方がその後良くなると考えています。
大事なのは、「家庭の外を見たら選択肢は増えるかも」ということです。

どうして“地域”という視点で課題解決を行おうと考えたのでしょうか。
ベースには人が好きという思いがあります。
人との繋がりがあるからこそ、自分を認められる。
言い換えると、「いろんな人」「いろんな場所」を知って多様な外部を認めることで自分も認めることができるというイメージです。
歳を重ねるとコミュニティが狭くなっていき、視野も狭くなってしまいます。
ただ、地域には多様な人がいて、刺激をもらって自分の可能性を広げていくことができる。
これからも地域の人達が周りの人を認めて自分も認めて、みんなが自分らしくありのままでいられる社会を作っていきたいです。

編集後記
地域の中で暮らしを作っていく方のお話を聞けてとても楽しかったです!
自分の体験を元に課題に対して挑戦していく、大企業の中でも手触り感のある仕事をしていると感じました。
これからの働き方を実践されていて学ぶことが多いインタビューの時間でした。